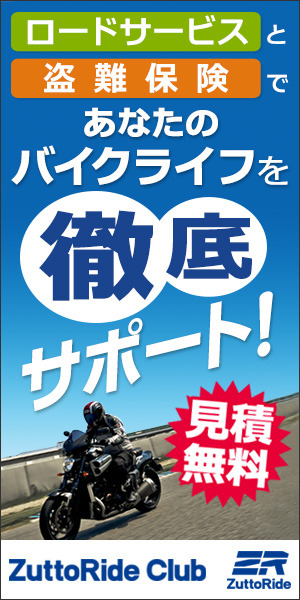ヤマハ YZF-R7が遂にモデルチェンジされました。兄弟車のMT-07のモデルチェンジに伴い、電スロ化され、電子制御が大幅に追加されたのです。今までのR7と比較して、どのような部分が変更されたのか、解説していきます。
目次 この記事の内容
- EICMA2025の発表
- YZF-R7 2026年モデルの特徴
- 外観やポジションについて
- 順当なアップデートの新型
EICMA2025の発表
![]()
ヤマハは、CP2エンジンの基本モデルとして、ストリートファイターのMT-07を2025年の冬頃にモデルチェンジを行いました。
このモデルチェンジで印象的だったのは、スロット・オブ・ワイヤである、YCC-Tを搭載し、更にオートマチック機能付きのY-AMTモデルを追加したことです。
そこから遅れて春頃にはデュアルパーパスバイク、テネレ700も電スロ化した新型を投入し、YZF-R7のアップグレードも期待されていました。そうこうしている内に、ヤマハは兄弟車のYZF-R9を秋に日本でも販売開始しました。
筆者が投稿した、この記事の動画バージョンです。
イタリア・ミラノショーであるEICMA2025で満を持してYZF-R7のモデルチェンジを発表し、2026年から販売開始されることとなったのです。
こうなると気になるのが従来型と比較して、どのような変更があったのか?そこに尽きると思います。そこで今回は、どのようにモデルチェンジされたか見ていきます。
YZF-R7 2026年モデルの特徴
![]()
2026年型 YZF-R7は、従来通り、689ccの水冷直列2気筒エンジンであるCP2エンジンを搭載しています。CP2は、クランク角度が270度であり、低い回転数から十分なトルクの出るエンジンとして、ヤマハの多くの車種に使われている名機です。
最大出力は73.4PS/8,750rpm、最大トルクは68N・m/6,500rpmです。車重は189kgで、燃料タンク容量は14Lです。軽い車体に十分なパワーのCP2による軽快な走りこそ、YZF-R7の最大の特徴と言えます。
しかし、2026年型のR7は、これまでとは違いYCC-Tを搭載しました。これにより、3つのライディングモードとカスタムモード2つを選択することができるようになりました。また6軸IMUを搭載しています。
トラコン、ローンチコントロール、リフトコントロール、ABS含めたブレーキコントロール、バックスリップレギュレーター、エンジンブレーキマネジメント、クルーズコントロール、第3世代クィックシフター(上下可能)。
これまでのR7と異なり、電子制御は全部載せと言った感じです。従来モデルは、アシスト&スリッパークラッチやABSくらいで、クィックシフターもアップ方向のみでオプション設定でした。
外観やポジションについて

以前のモデルよりも、全体的に鋭角的な感じになっています。大幅には変更されていませんが、新しいR3やR9に寄せたデザインでしょう。また、欧州仕様ではウィンカーがミラーに埋め込まれており、よりサイバー感が増しました。
従来モデルのイメージを踏襲しつつ、新しいRシリーズのミドルハイクラスのバイクとして、正統な進化と言えます。ラジアルマスターシリンダー、ラジアルマウントのブレーキや、レーシーな倒立フォークなど、これまで同様の豪華な足回りは健在です。
シート高は830mmとR1と比較すればマシですが、かなり高い部類になります。実際に従来モデルに跨ってみると、身長が173cmある筆者でも両足はつきますが、踵が少し浮きました。
またSSらしい前傾姿勢も以前のモデルと同じくらいのキツイものです。もちろん、R1やR6よりはマシですが。ただ、SSとしての前傾の深いポジションだと言えます。
シャシーも更なる見直しがはかられ、これまで以上のパフォーマンスが期待できるようになっています。標準装備のタイヤは、ブリヂストンのS23で、フロントが120/70ZR17、リアが180/55ZR17となっています。
順当なアップデートの新型

今後CP2エンジンは、Moto3にワンメイクのエンジンサプライヤーとして2028年より、提供される予定です。また、WorldWCR(FIM女子世界選手権)でも使われているR7のアップデートは必須でした。
電子制御の部分を強化することにより、より安全性が高まったと言えるでしょう。気になるのは、大幅なアップグレードによる価格の上昇で、現在のところ税込みで105万4,900円の車両価格がどこまで上がるかです。
個人的には、丁度いいパワーと扱いやすいトルクのCP2なので、従来型が安いままなら、こちらも有りかと思います。ただ、最新技術がてんこ盛りの新型は、魅力が増しているので、そちらを待つのもいいと思いました。